弔慰金の相続税は非課税?課税対象となるケースとは?

親族の不幸で弔慰金を受け取ったとき、「これは相続税の対象になるの?」と不安に思う方は少なくありません。
弔慰金は、故人を弔い、遺族を経済的に支えるために支払われる大切なお金です。しかし、その税務上の扱いについて正しく理解している人は意外と少ないのではないでしょうか。
この記事では、弔慰金と相続税の関係について、非課税枠の計算方法・香典や死亡退職金との違い・課税対象となるケース・申告の流れまでを詳しく解説します。
目次
弔慰金とは?その定義と種類

弔慰金とは、死亡した人の霊を慰め、遺族の精神的・経済的負担を軽減するために支払われる金銭のことです。香典が「葬儀に参列した人が霊前に供えるもの」であるのに対し、弔慰金は遺族の生活補助の意味合いが強いのが特徴です。
主な種類
企業からの弔慰金 従業員が死亡した場合に、会社から遺族に対して支払われるもの。就業規則や退職金規程で定められているケースが多い。
団体からの弔慰金労働組合や互助会などの団体から支給されるもの。共済制度など、会員同士の相互扶助を目的に支給される。
個人からの弔慰金親族や知人から渡されるもの。香典と区別が難しい場合もあるが、性質上「香典扱い」として非課税となることが多い。
弔慰金は原則として相続税の対象外
弔慰金は、原則として相続税の課税対象にはなりません。
理由は、弔慰金が「遺族の生活を支えるためのもの」であり、相続財産(預金や不動産など)とは性質が異なるためです。
ただし、社会通念上「相当」とされる金額を超える部分は、相続税の対象になります。
そこで重要なのが「非課税枠の計算方法」です。
弔慰金の非課税枠と計算方法
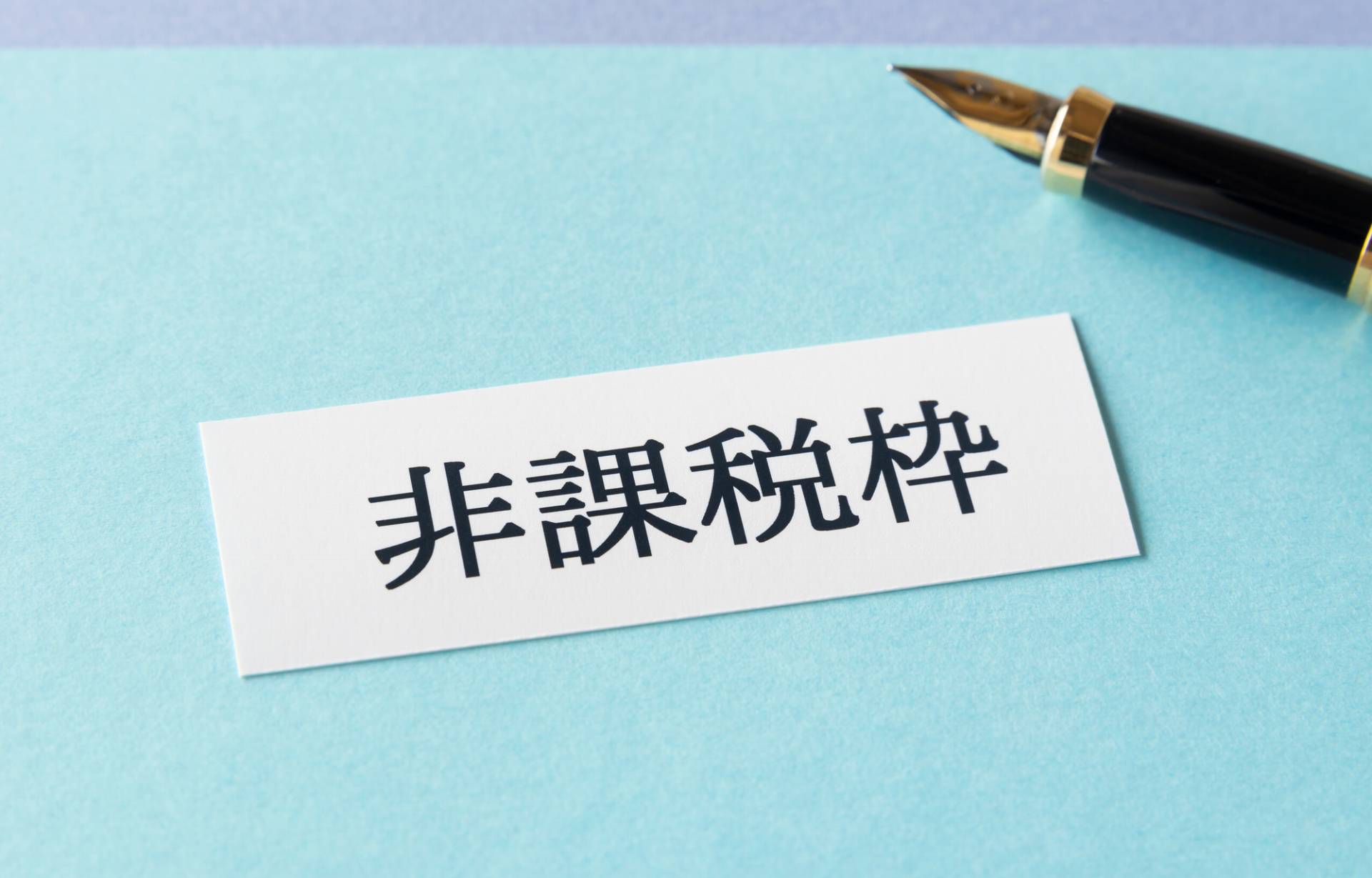
弔慰金には、相続税がかからない限度額(非課税枠)が設けられています。
非課税限度額
業務上の死亡の場合
亡くなった方の普通給与の 3年分
業務外の死亡の場合
亡くなった方の普通給与の 半年分
この範囲内の金額には相続税がかかりません。超えた部分は「退職手当金等」とみなされ、相続税の対象となります。
計算例
例:Aさん(業務外の事故で死亡)の月給が50万円、弔慰金が600万円の場合
非課税限度額:50万円 × 6か月 = 300万円
受け取った弔慰金:600万円
課税対象額:600万円 − 300万円 = 300万円
この300万円が相続財産に含まれ、相続税申告で計算に加える必要があります。
香典・死亡退職金との違い
香典は葬儀に参列した方が故人を悼むために贈るお金で、相続税はかからず、遺族が受け取っても非課税です。
死亡退職金は、故人が生前に勤務先で積み立てていた退職金を遺族に支払うもので、相続税の課税対象となりますが、法定相続人1人につき500万円の非課税枠があります。
整理すると以下の通りです。
- 弔慰金 ⇒ 原則非課税(一定額を超えると課税)
- 死亡退職金 ⇒ 課税対象だが非課税枠あり
- 香典 ⇒ 全額非課税
弔慰金が課税対象となるケース

弔慰金が例外的に相続税の対象になるケースには、次のようなものがあります。
高額な弔慰金を受け取った場合 非課税枠(給与3年分または半年分)を超える部分は課税対象となる。
退職慰労金や役員報酬とみなされる場合 名目は弔慰金でも、実質的に生前の労務対価とされる場合には課税対象となる。
性質が死亡退職金に近いと判断される場合
支給経緯や金額によっては、税務署が「弔慰金ではなく退職手当金等」とみなし、課税対象とされることもある。
相続税申告における弔慰金の取り扱い

弔慰金が非課税枠を超える場合、相続税の申告で「課税対象の財産」として申告する必要があります。
申告の流れ
- すべての相続財産を洗い出す
- 弔慰金の金額を確認し、非課税枠を計算
- 超過分を死亡退職金と同様に相続財産へ加算
- 基礎控除・各種特例を適用して相続税額を算出
- 相続開始から10か月以内に申告・納税
注意点
個人からの弔慰金には非課税枠がないため、基本的に全額非課税(香典扱い)か、贈与と判断される場合もあります。
また、企業からの弔慰金は、金額や支給理由によって課税対象かどうか変わるため慎重な判断が必要です。
まとめ
- 弔慰金は、原則として相続税の対象外
- 弔慰金の非課税枠は「業務上死亡=給与3年分」「業務外死亡=給与半年分」
- 非課税枠を超える部分は死亡退職金と同様に課税対象
- 香典は非課税、死亡退職金は課税ですが500万円×法定相続人の非課税枠がある
弔慰金は遺族の生活を支える大切なお金ですが、金額や性質によっては相続税がかかる場合があります。
判断を誤ると申告漏れにつながるため、不安な場合は税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
ニース税理士法人では、弔慰金や死亡退職金を含む相続税申告についてご相談を承っています。 「相続税の対象かどうか不安」「申告が必要か分からない」という方は、初回相談は無料で承っておりますので、ぜひ一度お問い合わせください。
【文責】
高瀬明彦
ニース税理士法人 シニアマネジャー
明治大学商学部卒業
2004年10月 監査法人トーマツ系列会計事務所入社
2007年3月 ニース税理士法人入社
2007年8月 税理士登録(登録番号:108496)
