株式の生前贈与は相続税対策になるの…?メリットや注意点を解説
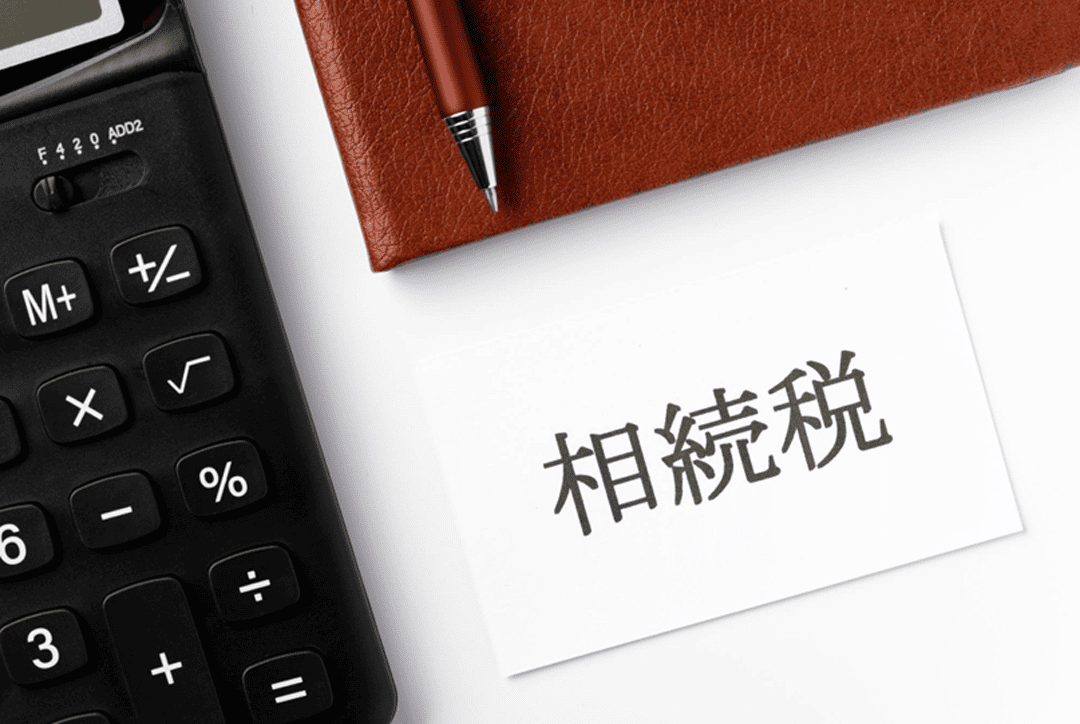
事業承継を考える経営者にとって、「株式の生前贈与」 は相続税の負担を軽減する有効な手段の一つです。しかし、贈与税や相続時の影響を考慮せずに進めると、思わぬ税負担が発生する可能性もあります。
今回は、株式の生前贈与が相続税対策としてどのようなメリットをもたらすのか、また注意すべきポイントについて詳しく解説します。
株式の生前贈与は相続税対策になる?
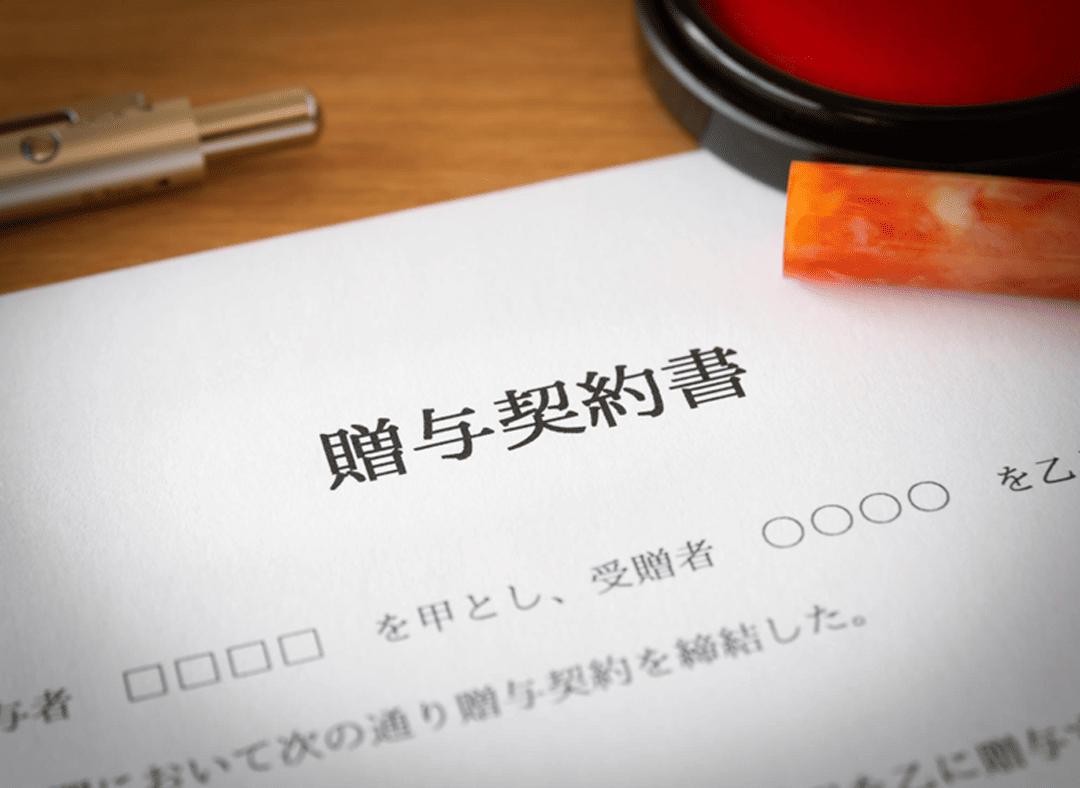
株式の生前贈与は「早期の贈与で相続財産が圧縮できる」「好きなタイミングで贈与できる」「事業承継税制が活用できる」という3つの理由により相続税対策になると言えます。
早期の贈与で相続財産が圧縮できる
相続税は、被相続人(亡くなった人)の死亡時の財産総額に対して課税されるため、生前に財産を贈与することで、相続時の財産総額を減らすことができます。
特に将来株価の上昇が見込まれる株式については早めに贈与することで、相続税の課税対象を大幅に圧縮することができます。
また、株式を生前贈与することで、贈与後に受け取る配当金は株式の贈与を受けた人(受贈者)に帰属することになるため、贈与をした人の相続財産の圧縮だけでなく、受贈者の財産形成にも繋がります。
好きなタイミングで贈与できる
未上場の自社株式の評価額は、経済環境や企業の業績によって変動します。
株価が低いタイミングで贈与を行えば、贈与税の課税対象となる額を抑えられるため、節税になります。
特に、創業初期や業績が一時的に低迷している時期に贈与すると、評価額を低く抑えることができます。
事業承継税制が活用できる
「事業承継税制(特例措置)」を利用すると、一定の条件を満たすことで、贈与税の100%の納税猶予・免除が可能になります。
(詳しくは、以前のコラム「事業承継税制とは何かをわかりやすく解説!メリット・デメリットも」参照)
事業承継税制とは何かをわかりやすく解説!メリット・デメリットも
この制度を適用すれば、多額の贈与税を支払うことなく、円滑に自社株式を後継者へ移転することができます。
株式の生前贈与の方法・メリット

株式の生前贈与は相続税対策になるということが分かったところで、次にその生前贈与の方法・流れや相続税対策以外のメリットについて解説します。
生前贈与の方法・流れ
下記の順序により進めるのが一般的な流れとなります。
自社株式の評価
贈与税は、贈与時の株式の相続税評価額をもとに計算されます。
非上場株式は、証券市場での取引がないため、原則として「類似業種比準価額方式」又は「純資産価額方式」を用いて評価します。
非上場株式の評価については、税理士など税の専門家に依頼することで適切な評価額を算定することができます。
贈与方法の選択
贈与には、下記のとおり、暦年贈与(暦年課税)と相続時精算課税の2つの方法があります。
目的や状況に応じて選択します。
| 暦年課税 | 相続時精算課税※1 | |
| 贈与者 | 誰でも | 60歳※2以上の父母や祖父母 |
| 受贈者 | 誰でも | 18歳※2以上の子や孫 |
| 非課税枠 | 基礎控除 | 基礎控除 |
| 年間110万円 | ||
| 年間110万円 | 特別控除 | |
| 相続開始まで累計2500万円 | ||
| 税率 | 非課税枠を超えた額の | 非課税枠を超えた額の20% |
| 10%~55%(累進税率) | ||
| 申告の必要性 | 110万円を超えると必要 | 110万円を超えると必要 |
| 届出の必要性 | 届出不要 | 最初に贈与を受けた年の翌年 |
| 3月15日までに届出が必要 | ||
| 生前贈与の加算 | 相続時開始前7年以内の贈与 | 毎年110万円超の額は過去にさかのぼって |
| は相続財産に加算する※3 | 全て相続財産に加算する |
※1 一度選択すると、同じ贈与者からの贈与は、暦年課税に戻すことはできない。
※2 年齢はその年の1月1日時点で判定する。
※3 相続又は遺贈により財産を取得した者に限る。令和8年末までの相続等では相続開始前3年以内。令和9年1月1日以降の相続等から加算期間が延びていき、令和13年1月1日以後の相続等から加算期間が7年となる。相続開始前3年超7年以内の相続財産のうち延長された4年分から100万円を控除する。
贈与契約書の作成
贈与を行うには、贈与者と受贈者との間で贈与契約の合意が必要です。贈与契約の合意は口頭で行うことができますが、トラブルにならないよう贈与があったことを証明するために贈与契約書を作成すると良いでしょう。
贈与の実行
贈与契約に従い、贈与を実行します。具体的には、株主名簿の書き換え、株式発行会社の場合には現物の株券の引き渡しを行います。
贈与税の申告と納付
受贈者は贈与を受けた日の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告及び納付を行います。
なお、贈与を受けた金額が非課税枠内であれば申告は不要ですが、証拠保全を目的として申告を行うケースもあります。
相続税対策以外のメリット
株式の生前贈与には、前述の相続税対策以外に下記のメリットがあります。
計画的な事業承継が可能
生前贈与をすることで、贈与後も先代経営者が存命のうちに後継者に対して時間をかけた育成や経営指導が可能となります。
また、自社の社員や取引先に前もって次の経営者を示すことでトラブルを未然に防ぐことができます。
将来の親族間の相続トラブルを防ぐ
生前贈与を行うことで、会社の後継者が明確になり他の相続人との「争族」トラブルを前もって防ぐことができます。
また、事前に親族間で合意形成ができるので、事業承継と相続発生後の遺産分割がスムーズになります。
株式の生前贈与に関する注意点やデメリット
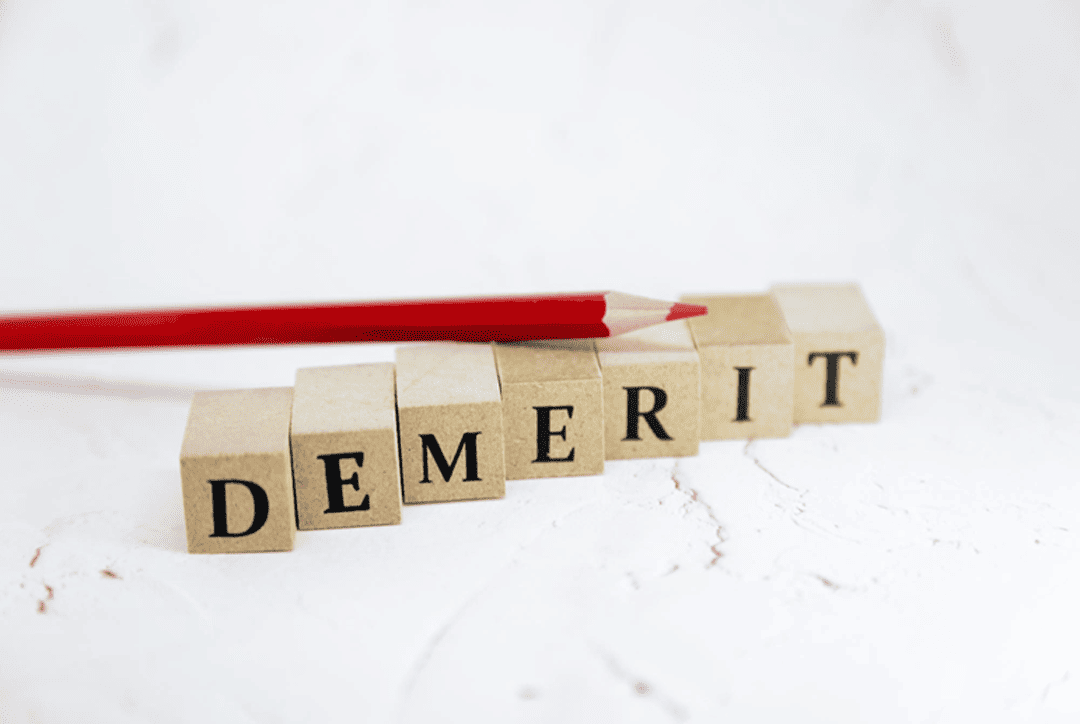
株式の生前贈与は、相続税対策や事業承継においてとても有効ですが、慎重に行わなければ思わぬリスクや税負担が発生します。ここでは、株式の生前贈与をする場合の注意点やデメリットについて解説します。
贈与税が発生する場合がある
贈与する株式の評価額が110万円を超える場合には、贈与税が発生します。 高額の株式を贈与する場合には、相続時精算課税制度や事業承継税制の活用をすることで贈与税をゼロ又は低く抑えることができます。
ただし、相続時精算課税制度は一回選択すると、その贈与者からの贈与に対しては暦年贈与に戻せなくなるため注意が必要です。
株式の生前贈与を受けなかった他の相続人への配慮が必要
株式の評価額は高額になることがあるため、株式を特定の親族だけに贈与し、他の相続人に渡す財産との間に金額の不均衡があると、相続後に「特別受益」や「遺留分侵害」の問題が生じる可能性があります。 そのため、株式を受け取らない相続人のことも考えて、その他の財産(現預金や不動産)を残すなど、財産の分配が偏らないよう配慮する必要があります。
贈与後の後戻りができない
贈与は基本的に「無償かつ取り消し不可」であり、一度贈与した株式を取り戻すことはできません。経営方針の違いや信頼関係に変化が生じた場合、贈与した株式を取り戻す法的手段は非常に限定的です。
そのため、後継者の適性をしっかり見極め、試用期間的な関与(役員就任など)を経てから贈与をするなどの対策が必要となります。
将来的に株価が下がった場合には損となる
贈与時に高い評価額で贈与した場合、将来的に株価が下がれば損となってしまいます。相続時に株価が下がってしまっていたら、贈与よりも相続の方が有利だったというケースもあります。
そのため、税理士などの専門家のアドバイスを受けた上で、会社の価値の推移を見ながら贈与のタイミングを図る必要があります。
相続や生前贈与に関するご相談なら
今回は、株式の生前贈与が相続税対策としてどのようなメリットをもたらすのか、また注意すべきポイントについて解説しました。
株式の生前贈与は、相続税対策としての節税効果はもちろん、後継者への事業承継を計画的に進められる点で非常に有効です。
ただし、贈与税の負担や各種制度の適用条件など注意すべき点が多々あるため、税理士などの専門家に相談の上、進めることを強くオススメします。
当ニース税理士法人では、相続税の試算、生前贈与・贈与税のご相談、自社株式の評価、遺産分割・特別受益・遺留分への対応など、経験豊富な税理士がチームでトータルサポート致します。
初回相談は無料です。どんな小さなご不安でも対応致しますので、ぜひお気軽にご相談ください。
【文責】
高瀬明彦
ニース税理士法人 シニアマネジャー
明治大学商学部卒業
2004年10月 監査法人トーマツ系列会計事務所入社
2007年3月 ニース税理士法人入社
2007年8月 税理士登録(登録番号:108496)
